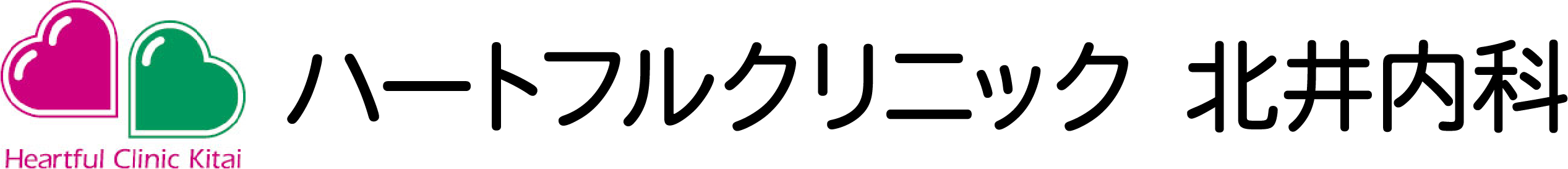肺気腫
肺気腫とは

肺には肺胞と呼ばれる数億個の小さな部屋がぶどう状に集まっています。この肺胞の壁には血管が張り巡らされており、吸い込んだ空気から酸素を血液中に取り込み、二酸化炭素を血液中から取り除くガス交換が行われています。
肺胞が小さな部屋に分かれているのは、肺胞の壁の表面積を増やしてガス交換を効率よく行うためです。肺気腫はこの肺胞の壁が破壊され、隣り合った肺胞同士が次々と合わさって大きな気腔を形成する病気です。
肺気腫では肺胞の壁の表面積が減るのでガス交換の効率が低下します。また、大きな気腔により気管支は圧迫され、息を吐くことが困難になります。破壊された肺胞は再生しないため、肺気腫は一旦発症するとゆっくりとながら進行し続けます。
日本には500万人もの肺気腫の患者がいると推定されていますが、実際に治療を受けている方は30万人ほどに過ぎません。
肺気腫の原因
肺気腫の原因の大部分は喫煙であり、その因果関係は明らかになっています。
肺には免疫に関係する白血球が数多く存在しており、空気中の有害な微生物や物質が肺に吸い込まれた際、体内に入り込まないように機能します。
たばこの煙や化学物質により白血球が活性化されると、たんぱく質を分解する酵素を放出します。この酵素は本来は細菌などを分解するために放出されますが、自分自身の肺胞壁をも溶かしてしまうため、肺気腫が起こると考えられています。
肺にはこの蛋白を分解する酵素に対する防御機能が備わっていますが、この防御機能は個人差が大きいため、同じ量のたばこを吸っても、肺気腫になりやすい人となりにくい人がいます。
肺気腫は何十年もかかって肺胞がゆっくり破壊された結果の病気であり、40-50歳代で最も多く発症します。
肺気腫の症状

息切れの症状が最も多くみられます。しかし、比較的高齢になってから発症する疾患のため、息切れの症状を「歳のせい」と考えて、見過ごされるケースが多いようです。
他に、咳・痰の症状がみられます。さらに病気が進行すると、低酸素により肺の血管が収縮し、体循環が停滞して浮腫が起こります(肺性心)。さらに、二酸化炭素が蓄積すると意識障害を来たすこともあります(CO2ナルコーシス)。また、肺気腫の症状は風邪を引いた場合に急激に悪化する特徴があります。
肺気腫の検査

胸部レントゲン、呼吸機能検査およびパルスオキシメーターを行います。
胸部レントゲンでは胸郭のビール樽様変形、横隔膜低位、心臓の圧迫(滴状心)がみられ、これは肺の膨張によるものです。
呼吸機能検査では一秒量(FEV1.0)、一秒率(FEV1%)、FEV1.0の予測値に対する割合(%FEV1.0)の低下を認めます。
また、パルスオキシメーターで酸素飽和度(SpO2)を測定して、低酸素血症の程度を知ることができます。
これらの検査は当院で行うことができます。喫煙者または喫煙歴のある方は定期的に検査を受けてください。
肺気腫の重症度(GOLD重症度分類)
%FEV1.0で分類され、症状は以下のようになります。
| 軽 症 | %FEV1.0≧80 症状はあっても咳・痰程度です。 |
|---|---|
| 中等症 | 80>%FEV1.0≧50 息切れ、慢性の咳・痰がみられます。 |
| 重症 | 50>%FEV1.0≧30 息切れがひどくなり、生活に支障がでます。 |
| 最重症 | 30>%FEV1.0 慢性呼吸不全状態のため全身状態悪化し、日常生活ができなくなります。 |
肺気腫の治療
肺は再生しない臓器であり、肺気腫は進行性の病気です。しかし、治らないからとあきらめる必要はなく、進行をゆっくりとさせることは可能です。まずは原因の除去が最優先であり、禁煙を大原則とします。
副流煙によっても肺気腫は進行するため、喫煙者の多くいる環境は避けたほうがよいでしょう。息切れ、咳・痰等の症状を改善する治療として気管支拡張薬があります。気管支拡張薬には抗コリン薬(スピリーバ等)とβ2刺激薬(セレベント、ホクナリンテープ等)があります。肺気腫の場合は、気管支喘息とは異なり抗コリン薬の方が有効ですが、症状により併用されることもあります。
気管支拡張薬により症状を改善させることができますが、肺気腫を根本的に治療しているわけではありません。症状が軽くなったからといって喫煙を再開するのは厳禁です。
肺気腫が進行すると少し歩いたり、着替えたりするだけで呼吸困難が起こるようになります。このような人には薬だけでは症状の改善が不十分であり、在宅酸素療法が行われます。自宅で酸素吸入をしたり、外出時に酸素を携帯することはわずらわしく思われがちですが、在宅酸素療法により患者さんの行動範囲は著しく拡大することができます。在宅酸素療法の原因疾患で最も多いのが肺気腫であり、約40%を占めています。
また、風邪やインフルエンザにより肺気腫は急激に悪化することがあり、定期的なうがいとインフルエンザワクチン接種が推奨されています。
肺気腫と食事

肺気腫が進行すると、食事をするだけでも息切れをおこすようになります。また、食事により胃が膨らみ横隔膜が上方に圧迫され、肺容積が減少し、ますます呼吸困難になります。このため、十分な栄養を摂取できず痩せてしまうことが多く、やせにより呼吸筋も減少するためさらに呼吸困難が悪化します。
肺気腫に対する特別な食事療法はありませんが、高カロリー、高蛋白質食が呼吸筋機能の維持のために必要です。ただし、肥満の方は呼吸筋の動きをスムースにするために、減量が必要です。
肺気腫と運動

肺気腫の方は運動により呼吸困難が起こるため、家の中にひきこもりがちになります。しかし運動をしないと呼吸筋の機能が低下し、ますます呼吸困難が悪化します。この悪循環を断ち切るため、適度な運動は必要です。
腹式呼吸の訓練を主体に呼吸練習を行います。息を吸うときにおなかをふくらませ、息を吐くときにおなかをへこませて、胸はあまり動かさないように呼吸します。また、呼気時の気道閉塞を緩和するために、口すぼめ呼吸を行います。呼吸練習は寝た状態から始めて、側臥位、座位、立位へと練習し、立位で腹式呼吸ができるようになったら歩行、階段昇降へと練習を進めていきます。
肺気腫とたばこ

肺気腫の原因のほとんどが喫煙習慣であるため、禁煙が絶対的に必要です。気管支拡張薬の使用により、肺気腫の症状を改善させることができますが、根本的な治療法はありません。症状が軽くなったからといって、たばこを吸うのは本末転倒です。
当院では禁煙外来を開設しています。健康保険で禁煙補助薬(内服薬または貼付薬)が処方可能です。たばこを吸う方は、ぜひ受診してください。
肺気腫とアルコール

お酒は肺気腫に悪影響を及ぼすことはありません。しかし、肺気腫に気管支喘息が合併していることがあり、この場合はアルコール誘発性喘息の危険があるため注意が必要です。

肺気腫のまとめ
肺気腫はたばこを原因とする進行性の疾患です。症状が進行してからでは改善の余地は乏しいため、喫煙者または喫煙歴のある方は定期的な検査が必要です。無症状であるか症状の軽いうちに進行を予防すれば、肺気腫に伴なう生活の制限を受けずに済むかもしれません。 早期発見、早期治療が重要であり、原因を絶つために禁煙が必要です。