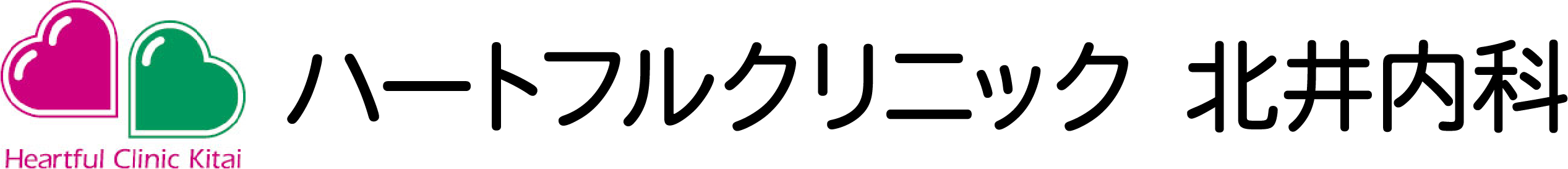高尿酸血症・痛風
高尿酸血症とは

食物中に含まれるプリン体が体内で分解されて、最終的に尿酸になります。また、体内に含まれている核酸やATPも消費、分解されてプリン体から尿酸となります。
尿酸の80%は尿中に排泄されますが、尿酸は水に溶けにくいため、その排泄には限りがあります。この尿酸の生産と排泄のバランスの乱れにより、血液中の尿酸が高くなった状態が高尿酸血症です。日本人の場合、大部分は尿酸排泄の低下が原因となっています。
痛風とは
なんらかの原因で血液中の尿酸の濃度が上昇して飽和濃度を越えると、尿酸はナトリウムと結合して針状の尿酸結晶となります。この尿酸結晶が関節等に蓄積して、白血球との間で炎症が起こった状態が痛風(痛風発作)です。
尿酸結晶は体温の低い部位に蓄積しやすいため、 痛風は足の親指の付け根に発症することが最も多く、 他にくるぶし、膝関節、アキレス腱に好発します。 症状は字のごとく「風が吹いても痛い」ほどの激痛です。
日本には50-60万人の痛風患者がいると推定されています。痛風の症状

患部の激痛、発赤、発熱、腫れを痛風の4大徴候といいます。
関節の違和感から始まり、徐々に痛みが起こり、24―48時間後に激痛となります。2-3日激痛がつづいた後、徐々に痛みは和らいでいき、2週間程度で消失します。
痛みがなくなると、完治したと思われがちですが、放置すれば半年から1年ほどで再発し、その発作の間隔は次第に短くなります。さらに進行すると、腎臓などの内臓まで侵されるようになります。
痛風になりやすい人とは
以前、痛風は「帝王病」や「ぜいたく病」といわれていましたが、現在では食生活の欧米化に伴い「一般病」となってきています。
動物性食品、アルコールにはプリン体が多く含まれているため、大食家や大酒家に痛風が多くみられます。
また、激しい運動により尿酸値が上昇するため、スポーツ選手にも多くみられます。肥満の人は尿酸の排泄が低下するため、太ると痛風になる危険性が高くなります。また、「積極的」、「活動的」、「責任感が強い」といった性格の人は、肉体的にも精神的にもストレスがかかりやすいため、痛風にかかりやすい傾向があります。
痛風患者の99%は男性で、30-50歳台にもっとも多く発症します。女性が痛風になりにくいのは、女性ホルモンが尿酸の尿中排泄を促進するためといわれています。しかし、現代社会のストレスや食生活の変化により、痛風にかかる若い女性の割合が徐々に増えています。
高尿酸血症の合併症
血中の尿酸値が7.0ml/dlを越える状態が数年間続くと痛風発作が起こる可能性があります。しかし、高尿酸血症は痛風だけではなく、腎結石、尿管結石や腎不全を併発する危険性があります。
また、高尿酸血症自体が動脈硬化の促進因子であるため、脳梗塞、心筋梗塞等の重篤な疾患を合併する可能性が高く、痛風発作の経験がなくても高尿酸血症の治療は必要です。当院では、採血後15-45分程度で尿酸の測定ができます。飲酒習慣のある方や検診等で高尿酸血症を指摘された方は、定期的な検査を受けて、自分の尿酸値を把握することが大切です。
高尿酸血症の治療

食事、飲酒、肥満の是正が治療の基本です。溶けにくい尿酸の排泄の効率を上げるため、1日2リットル以上の水分をとるようにしましょう。治療薬には尿酸の合成を抑制する薬と、尿酸の排出を促進する薬があり、高尿酸血症の原因、程度、および合併症の有無により使い分けます。
また、痛風発作時に尿酸を低下させると痛みが強くなることがあり、発作時には痛みを緩和する治療が優先されます。
痛風発作の治療
痛風発作時は、患部を冷やすこと、安静にすること、禁酒が治療の基本になります。痛風発作の予兆期やごく初期にはコルヒチンという薬が有効です。しかし、痛風発作が本格的になるとコルヒチンの効きは悪くなり、非ステロイド系抗炎症薬や副腎皮質ステロイド薬が必要となります。
高尿酸血症の食事療法

レバー、えび、魚の干物にはプリン体が多く含まれていますので、避けた方がいいでしょう。逆に牛乳、卵、豆腐、鶏肉、アジ、マグロ等は高蛋白・低プリン体食品ですので、積極的に摂取したいものです。痛風・尿路結石の予防のため、水分を十分摂ってください。。1日の目安としては、食事以外で2,000ml以上が必要で、1,000ml以下では尿路結石の発症率が高まることが知られています。また、痛風患者の60%の方が肥満体型です。このため、肥満の人は低カロリー食を基本としましょう。芋類、野菜、海藻、きのこ類を取り入れたバランスのよい食事を心がけるといいでしょう。
高尿酸血症と運動

適度な運動は高尿酸血症の合併症の予防と治療に有用です。特にウォーキングなどの有酸素運動は尿酸値を下げる効果があるとされ、痛風患者に多い高血圧などの合併症にも有効です。
逆に急に激しい運動をすると尿酸の合成が促進され、乳酸が増加して尿酸の排泄が一時的に低下します。また、汗の中には尿酸はほとんど排出されないので、発汗により血液が濃縮して尿酸値が上昇します。運動中および運動後には十分な水分補給をし、運動の後の飲酒は避けて下さい。
高尿酸血症とたばこ

喫煙により痛風発作が起こりやすくなる訳ではありません。しかし、高尿酸血症と喫煙習慣があいまみえると、動脈硬化はさらに促進することになり、脳梗塞、心筋梗塞等の重篤な合併症の発症率は高くなります。やはり、禁煙は必要です。禁煙が困難とお感じの方は、ぜひ禁煙外来を受診してください。
高尿酸血症とアルコール

完全な禁酒が理想的ではありますが、なかなか実行するのは難しいものです。お酒の中で最もプリン体を含んでいるのはビールであり、最も少ない焼酎の180倍も含んでいます。しかし、焼酎なら飲んでも大丈夫という訳ではありません。アルコール自体に尿酸の合成を促進し、排泄を低下させる作用があるからです。
また、アルコールには食欲増進作用があるため、ついついカロリーオーバーとなりがちで、肥満の原因となります。1日の酒量の目安としては、ビールなら500ml、焼酎なら100ml、日本酒なら1合までです。普段はアルコールを飲まなかったとしても、宴会等で「どか飲み」した場合、数日後に痛風発作が起こりやすいことが知られています。あくまでも1日量の許容範囲内で嗜んでください。

高尿酸血症・痛風治療のまとめ
痛風は激痛を伴いますが、発作が治まると、なにごともなかったように感じられがちです。しかし、なんの対策も講じないと痛風発作は必ず再発し、しかもその周期はだんだんと短くなります。また、高尿酸血症の合併症は痛風だけではなく、重篤な動脈硬化疾患をも起こし得ます。症状がないときからの生活習慣の是正と治療が必要です。