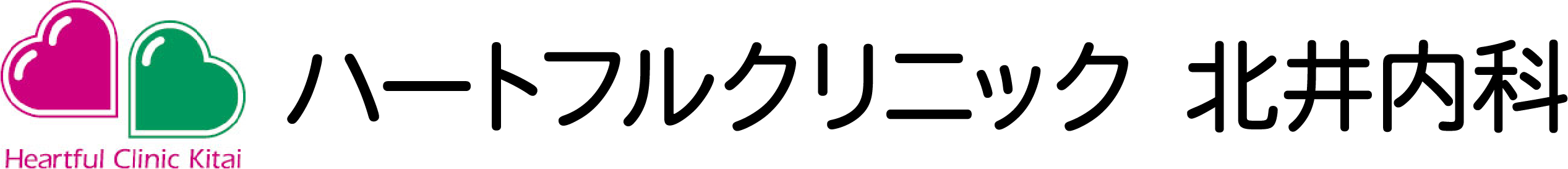糖尿病
糖尿病とは

血液中のブドウ糖を血糖といい、その濃度を血糖値といいます。
この血糖値が異常に高くなった状態が糖尿病です。
糖尿病はその名前から「尿に糖がおりる病気」と思われがちですが、これは必ずしも正しくなく、尿に糖がおりてなくても血糖値が異常に上昇していれば糖尿病です。
また逆に尿に糖がおりていても血糖値が正常であれば糖尿病ではありません。
わが国でも食習慣が欧米化し高脂肪食・高カロリー食となったことと、自動車の普及に伴う運動不足によって、糖尿病は増加しています。
現在、日本の糖尿病患者は740万人以上に及び、糖尿病を否定できない予備軍は900万人以上いると推定されています。
糖尿病は年齢とともに増加して、40歳以上の10人に1人が糖尿病です。
このように、中年以降は非常に身近な病気となっています。
糖尿病の原因
空腹時には血糖値が低くなるため、グルカゴン、アドレナリン、コルチゾール等のホルモンが分泌され、血糖値を上げるように作用します。
逆に、食後に血糖値が高くなったときに、血糖値を下げるように働く唯一のホルモンがインスリンです。
インスリンは膵臓から分泌され、主に血液中のブドウ糖を筋肉や脂肪などの細胞に送り込んで、血糖値を低下させます。
この、インスリンの分泌が不足したり、インスリンの分泌のタイミングが遅れたり、インスリンの作用が弱まったりすると、血糖値が上昇し糖尿病となるのです。
糖尿病になりやすい体質は遺伝の関与もあります。
しかし、糖尿病が増え続けていることからも分かるように、
過食、肥満、運動不足等の環境的な要因によって、糖尿病になる可能性は高まります。
糖尿病のタイプ
糖尿病は1型と2型に分類され、その他に二次性糖尿病と妊娠糖尿病があります。
1型糖尿病
1型糖尿病は、
膵臓のインスリンを分泌する細胞(β細胞)が破壊され、インスリンの分泌が絶対的に不足して起こります。
その多くは突然に発症し、急速に悪化するのが特徴です。
1型糖尿病は日本人には少なく、糖尿病全体の3-5%程度であり、通常20歳未満で発病します。
発症機序はまだ完全には解明されていませんが、免疫の異常により自らのβ細胞を攻撃・破壊してしまう自己免疫反応が関係していると考えられています。
2型糖尿病
2型糖尿病は、インスリンの分泌不足と作用低下により起こります。
いつ発症したか分からないままに、ゆっくりと進行していくため、健診などで偶然発見されるといったケースがよくみられます。
成人になってから発症する糖尿病のほとんどが2型であり、日本人の糖尿病の95%以上を占めています。
2型糖尿病はもともと遺伝的に糖尿病になりやすい体質を持っている人に、過食、運動不足、肥満、ストレスなどの環境要因が発症の引き金になって発症するケースが多くみられます。
二次性糖尿病・妊娠糖尿病
二次性糖尿病は膵炎や肝炎等のほかの病気に合併したり、ステロイド等の薬が原因となって発症する糖尿病です。
その多くは原因を取り除くことにより改善できます。
妊娠糖尿病は妊婦の2-4%にみられます。
妊娠中には普段より膵臓に負担がかかることと、胎盤からインスリンの作用を減弱させるホルモンが分泌される ことから糖尿病が発症します。
その多くは一時的なもので出産後は正常に戻ります。
しかし、数年後に2型糖尿病を発症する場合があり、特に4kg以上の子供を出産した場合に多くみられます。
糖尿病の症状
糖尿病の症状は、尿量の増加、のどの渇き、倦怠感、体重減少が代表的です。
さらに血糖値が高くなると、吐き気、腹痛、さらには意識障害が起こることもあります。
しかし、これらの症状は糖尿病が進行して、かなり血糖値が高くなってから起こるものであり、初期の段階ではほとんどが無症状です。
このため、治療を受けている糖尿病患者は全体の4分の1以下と推定されています。
本来は症状がでる前に治療が始められるべきです。
なぜならば、糖尿病の最も怖いところは、後述する合併症が起こることにあるからです。
糖尿病の合併症
糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害は細小血管の障害によって起こる糖尿病に特有の合併症であり、糖尿病の三大合併症と呼ばれています。
これらの合併症は高血糖状態が長く続いたことにより発症します。
糖尿病の三大合併症とその他の合併症を以下に説明します。
糖尿病性網膜症

網膜には眼球に栄養や酸素を運ぶための毛細血管がたくさん集まっています。
糖尿病発症から15年で、約半数が出血したり血流が悪くなるなどの網膜症を起こします。
最終的には網膜剥離、失明などの深刻な視覚障害を引き起こします。
現在、成人の失明原因の第一位は糖尿病性網膜症です。
網膜症の進行は初期段階の「単純網膜症」から始まり、「前増殖網膜症」を経て、最終段階である「増殖網膜症」へと進んでいきます。
初期の単純網膜症では、もろくなった網膜の毛細血管に小さなコブができます。
このコブが破れると点状出血が起こり、
脂肪やたんぱく質がしみ出して網膜上に沈着し、白斑が形成されます。
この段階では無症状症であり、血糖をコントロールすることにより、進行を抑えることができます。
単純網膜症では3-4ヶ月に1度の眼科的な定期検査を必要とします。
前増殖性網膜症では点状出血や白斑の数が増え、大きな眼底出血が出現します。
網膜に血流の不足する領域ができますが、
病変は網膜内にとどまっているため、ほとんど自覚症状がありません。
この段階での治療は、血糖コントロールに加えて、レーザー光凝固と呼ばれる治療が効果的です。
これは、レーザーで網膜の一部を焼いて小さなやけどをつくる治療で、点状出血や白斑を消滅させることができ、増殖網膜症への進行を防ぐことができます。
前増殖性網膜症では1-2ヶ月に1度の眼科の定期検査を必要とします。
増殖性網膜症では網膜の毛細血管の血流障害が進行し、新生血管と呼ばれる非常にもろい血管が発生します。
新生血管は血圧上昇などのわずかな刺激で破れて出血します。
その出血が網膜にとどまらず硝子体に起こると視力が低下し、視界がぼやけたり、黒い点がちらつくなどの自覚症状が出現します。
硝子体内に大出血が起こると、失明に至ることもあります。
新生血管の出血が繰り返されると、網膜と硝子体の間に増殖膜が形成されます。
この増殖膜が網膜を引っ張るため、「牽引性網膜はく離」が起こり、ものがゆがんで見えたり、
視力が極端に低下する症状が現れます。
網膜はく離が黄班部で起こると失明に至ります。
病変が網膜内にとどまっていれば、レーザー光凝固治療が有効です。
硝子体出血、網膜はく離が出現した場合は、硝子体や増殖膜を切除する手術を必要とします。
硝子体出血に至った場合は、2週間に1度の眼科の定期検査を必要とします。
また、新生血管の大出血を予防するため、激しい運動は厳禁です。
以上のように、糖尿病性網膜症は増殖性網膜症になるまでは自覚症状がないため、早期発見のために定期的な眼底検査が不可欠です。
糖尿病の方は眼底病変がなくても、1年に1度の眼底検査を受けるようにしましょう。
糖尿病性腎症
腎臓は体内の血液をろ過し、不要な老廃物を尿として排出する役割を担っています。
腎臓に送られた血液は、毛細血管が球状に密集している糸球体でろ過されます。
糖尿病で高血糖が続くと、糸球体のフィルター機能が低下し、老廃物が十分にろ過されず体内に蓄積したり、
本来はろ過されないはずのたんぱく質が尿中に排出されるようになります。
糖尿病腎症の早期には自覚症状がほとんどないため、定期的に尿検査や腎機能検査を受ける必要があります。
腎臓病というと尿に蛋白がでる蛋白尿がよく知られていますが、蛋白尿がでるのはかなり進行してからです。
この段階ではすでに腎機能の低下を伴っていることが多く、回復させるのは困難です。
蛋白尿がでる前であれば、腎症の進行を止めることが可能です。
初期の腎症を発見するため、尿中微量アルブミン検査を行います。
これはアルブミンというごく微量の蛋白質が尿中にでているかを調べる検査です。
糖尿病性腎症は、以下のごとく第1期から第5期までの段階に分けられます。
第1期 腎症前期
第1期は「腎症前期」とも呼ばれ、微量アルブミンおよび蛋白尿も陰性であり、腎機能検査も正常である状態です。
第2期 早期腎症
第2期は「早期腎症」と呼ばれ、微量アルブミン尿のみ認められ、蛋白尿は認めず、腎機能検査は正常である状態です。
一般に糖尿病を発症してから10-15年経過すると、第2期に移行します。
第3期 顕性腎症
第3期は「顕性腎症」と呼ばれ、持続的な蛋白尿が認められる状態です。
第3期は前期と後期に分かれ、前期は腎機能正常ですが、後期では腎機能の低下がみられます。
後期では、血圧の上昇や足のむくみなどの自覚症状がみられるようになります。
一般に、第2期から10年経つと第3期に移行します。
第4期 腎不全期
第4期は「腎不全期」と呼ばれ、腎機能がほとんど失われた状態です。
この時期になると慢性的に貧血状態になり、倦怠感、全身のむくみなどの症状が現れます。
さらに進行すると、全身に中毒症状が現れる尿毒症に陥り、肺水腫や脳の神経機能障害を併発し、透析療法を行わない限り、生命の維持ができなくなります。
第3期を5年間治療しないでいると、第4期に移行するといわれています。
第5期 透析療法期
第5期は「透析療法期」と呼ばれ、透析療法を導入した段階です。
第2期までなら、治療により回復が期待できます。
早期発見・早期治療が必要です。
尿病性神経障害

人間の末梢神経には、痛みや温度を感じる知覚神経、筋肉の動きを調節する運動神経、内臓とホルモンの分泌を調節する自律神経があります。
高血糖により末梢神経の細胞の機能が損なわれると、体の各部位に不調を起こします。
知覚神経と運動神経の障害は、糖尿病発症後の早い時期から現れます。
初期症状としては、手足のしびれ・痛み・感覚鈍磨が最も多く、他にこむら返り、筋力の低下などがあります。
これらの症状は下半身に初発することが多く、活動時より睡眠中に起こりやすいという特徴があります。
自律神経に障害が及ぶと、多汗、冷えやほてり、便秘や下痢、排尿障害、立ちくらみなどの症状が現れます。
神経障害が進行すると、痛みなどの刺激を伝達できなくなるため、合併症の発見が遅れたり、命に関わる事態を招くことがあります。
例えば、狭心症を併発した場合、通常は胸痛などの症状がありますが、糖尿病性神経障害があると、この狭心症の症状を感じなくなってしまいます。
そして突然の心筋梗塞や心不全といった重篤な発作を起こすことがあるのです。
同様に、足に小さな傷や感染が生じても、その痛みに気づかず潰瘍や壊疽に陥って、足の切断を余儀なくさせられることもあります。
このため、足の神経に神経障害が出現した方は、とがったものを感じにくくなっているため、裸足のままでいないようにしましょう。
糖尿病神経障害はさまざまな症状を起こしますが、いずれも治療の基本は血糖をコントロールすることにあります。
初期段階であれば、神経障害を回復させ、症状をなくすことも可能です。
その他の糖尿病の合併症
三大合併症以外には、動脈硬化性疾患、白内障および緑内障、感染症、足の壊疽が挙げられます。
糖尿病により動脈硬化が起こりやすくなるため、狭心症や心筋梗塞などの心臓病、脳出血や脳梗塞などの脳血管障害といった、命に関わる重大な合併症が引き起こされます。
また、足の動脈が詰まる下肢閉塞性動脈硬化症が合併することもあり、足の壊疽の原因にもなります。
白内障は眼の水晶体が白く濁る病気であり、濁りが光の通過を妨げたり、乱反射を起こすために、ものが見えにくくなります。
水晶体の濁りは加齢によって起こる一種の老化現象ですが、糖尿病によって発症の時期が特に早くなる傾向があります。
緑内障は眼圧の上昇により視神経が障害を受けて、視力が落ちたり視野が狭くなる病気です。
角膜と水晶体の間を房水という液体が満たしており、眼圧上昇時には偶角という排水溝から房水が排出され、眼圧は一定に保たれます。
しかし、糖尿病性網膜症により新生血管が生じて偶角をふさいでしまうと、眼圧が上昇する「血管新生緑内障」が起こります。
緑内障が発症すると眼の激痛、視力低下、吐き気、頭痛などの症状が現れますが、神経障害を合併している場合には症状を感じないこともあります。
障害を生じた視神経は回復しないので、治療が遅れると高い確率で失明に至ってしまいます。
感染症とはウイルスや細菌等の病原体によって起こる病気の総称です。
体内に病原体が侵入すると、病原体を排除しようと免疫システムが働き、血液中の白血球が中心的な役割を果たします。
しかし、血糖値が高い状態では白血球の働きが低下し、病原体を攻撃する力や抗体を作る力が減弱します。
逆に病原体は血糖を栄養源にするため、高血糖状態ではますます増殖していきます。
また、動脈硬化があると血流障害部には十分な酸素と栄養がいきわたらないため、抵抗力がさらに低下して感染が起こりやすくなります。
加えて、血流障害のある感染部には白血球が到達しにくいため、回復力も低下します。
また、神経障害を合併している場合は、感染症の症状に気づかずに治療が遅れるケースが多くみられます。
糖尿病性壊疽とは、靴ずれ、やけど、水虫などのちょっとした傷や感染症が悪化して、潰瘍や壊疽になる状態です。
これには血管障害から起こるものと、神経障害によりおこるものがあります。
血管障害による壊疽は、動脈硬化により足先の血流が悪くなって起こります。
細菌を殺す白血球や傷の回復を促す血液成分が病変部にいきわたらないために、小さな傷でも感染をおこしやすくなり、潰瘍や壊疽へと悪化します。
一方、神経障害による壊疽は、痛みを感じる神経が麻痺して鈍感になり、小さな傷に感染を起こしていることに気づかずに悪化させてしまい、潰瘍や壊疽に至ってしまいます。
血管障害と神経障害が同時に起こっていることも少なくありません。
いずれの原因でも、治療が遅れると壊疽が広がっていき、足の切断を余儀なくさせられることになりかねません。
普段から足の状態を注意することが必要です。
糖尿病の健診での検査

糖尿病の初期ではほとんどが無症状であるため、健診などで初めて糖尿病の疑いを指摘されるケースがよくみられます。
健診で行われる検査は主に、尿検査(尿糖、尿蛋白)、血液検査(血糖、HbA1c、血清クレアチニン)です。
尿検査では尿糖および尿蛋白の有無を調べます。
尿糖が出現するのは一般に血糖値が160-180以上になってからですので、すべての糖尿病患者を発見することができず、逆に尿糖が陽性だからといって必ずしも糖尿病とは限りません。
尿蛋白の有無を検査しているものの、健診では尿中微量アルブミンの検査はしておらず、2期以前の糖尿病腎症を発見することができません。
血糖検査では主に空腹時血糖が測定されます。
空腹時血糖は110未満が正常であり、126以上の場合、糖尿病が疑われます。
しかしながら、実際は空腹時血糖が110未満であっても、糖尿病であるケースは少なくありません。
HbA1cにより過去1-2ヶ月の血糖値の平均を推測することができます。
赤血球の構成成分であるヘモグロビンはブドウ糖と一度結合すると赤血球の寿命(約3-4ヶ月)まで離れないという性質があり、血糖値が高いほどより多く結合します。
HbA1cはヘモグロビン全体に対するブドウ糖の結合したヘモグロビンの割合であり、糖尿病のコントロールが悪いほどHbA1cは高値になります。
しかし、血糖値が数時間高い状態が続かないと、ヘモグロビンとブドウ糖は新たに結合せず、糖尿病の初期ではHbA1cが正常であることが多く見受けられます。
HbA1cは治療効果判定には最も重要視されていますが、糖尿病の早期発見には不向きといえます。
血清クレアチニンは腎機能低下に伴い上昇し、腎機能の簡単な指標になります。
しかし、筋肉量の少ない高齢者では腎機能が低下していても正常範囲内であることが少なくありません。
以上のように、健診ではおおよその状態しか把握できません。
このため、糖尿病の疑いがある方には、精密検査が必要です。
糖尿病の診断
糖尿病の診断のために、特に初期の糖尿病を見落とさないために、ブドウ糖負荷試験を行います。
まず空腹状態で血糖値を測定し、次に75g(=300kcal)のブドウ糖液を飲んだ2時間後に再び血糖値を測定します。
空腹時血糖値 126以上または、ブドウ糖負荷試験2時間値 200以上のいずれかに該当すれば糖尿病型と診断されます。
糖尿病の診断基準
糖尿病型の人が次の3項目いずれかに該当する場合、糖尿病と診断されます
- 糖尿病の症状(口渇、多飲、多尿、体重減少)がある
- HbA1cが6.5以上
- 糖尿病性網膜症がある
以上のいずれにも該当しない場合は日を改めて検査し、空腹時血糖 126以上ブドウ糖負荷試験2時間値 200以上随時血糖値 200以上のいずれかに該当すれば、糖尿病と診断されます。
また、糖尿病型には該当しないものの、空腹時血糖 110以上126未満または、ブドウ糖負荷試験2時間値 140以上200未満の場合を、境界型と分類されます。
当院ではブドウ糖負荷試験を行っております。
健診等で糖尿病を疑われた方は、一度御相談下さい。
糖尿病の治療の基本
糖尿病と診断されたら、自覚症状の有無に関わらず治療を開始する必要があります。
放置すると確実に悪化する病気であることと、合併症が発症するからです。
合併症は境界型糖尿病の段階から起こるため、早期発見・早期治療が重要です。
糖尿病の治療は、薬を飲んで安静にしていればよいわけでなく、手術でよくなるとういうものでもありません。
糖尿病の治療の3本柱は、食事療法、運動療法、そして薬物療法です。
糖尿病の食事療法
食事療法はすべての糖尿病患者が行う治療の要です。
内服薬やインスリン注射で血糖をコントロールする場合でも、食事療法をしっかり行っていることが前提となります。
糖尿病だからといって食べてはいけないものはなく、逆に食べれば糖尿病がよくなるものもありません。
食事療法の基本は
- 適正なカロリーをとる
- バランスよく栄養をとる
- 決まった時間に食事をし、まとめ食いをしない
の3点です。

適正カロリーは、体格や活動量によって個々に違い、標準体重に活動量に応じた数値を掛け合わせることにより計算されます。
標準体重は、身長×身長×22で求められます。
活動量に応じた数値は、主に部屋の中で生活している事務職や主婦業の方なら25、特に重労働をしていないセールスマン、販売員なら30、重労働をしている肉体労働者、運動選手なら40です。
例えば、身長170cmの事務職の人なら、1.7×1.7×22=63.6kgが標準体重であり、適正カロリーは、63.6×25=1,590kcalとなります。
「栄養をバランスよくとる」という言葉は漠然としていて、説得力がないようです。言葉を代えれば、1日に30品目以上の色々な種類の食品を摂るということになります。積極的に摂りたいものとしては、ビタミン、ミネラルが豊富で低カロリーである野菜類、血糖の急激な上昇を緩やかにする食物繊維を多く含んだきのこ、海藻、こんにゃく類です。
逆になるべく控えたいものとしては、砂糖を多く含むお菓子や清涼飲料水です。
間食は膵臓に負担をかける時間が増えるので、運動前後以外は避けた方が無難です。
特に、速効性の内服薬やインスリンを使用している方では、間食の時に薬が作用しておらず血糖が急上昇することがあります。
食事療法を始めると、多くの人が以前より食事の量を制限されるため、空腹感と欲求不満を感じるかもしれません。
最初は物足りなく感じる食事でも、続けているうちに慣れることができます。
また、面倒と思われるカロリー計算も、自然と身につくものです。
食事療法の工夫
以下に食事療法の物足りなさを補う工夫を列記します。
- 脂肪の少ない食材を選び、食べれる量を増やす
- 肉類なら脂肪の少ない赤身を、魚なら脂の多いぶり、さば、まぐろを避けて、たらやかれいといった白身魚を選びましょう。
- 低カロリー食品を用い、ボリューム感をだす
- きのこ、海草、こんにゃく等の低カロリー食品を積極的に活用しましょう。
- 見た目のボリュームを増やす
- 肉なら骨付き、魚なら尾頭付き、貝なら殻付きを用いて、ボリューム感を出す。
食べるのに時間がかかるため、早食い防止にもなります。 - 水分の多い料理を取り入れる
- 食事の最初にスープや汁物を飲んで、ある程度おなかをふくらましておく。
また、ご飯を雑炊にすれば、水分による増量効果もあります。 - 料理の品数を増やす。
- 食卓にたくさんの器が並んでいると、見た目の満足感が増えます。
- ゆっくり食べる
- 食事をはじめてからしばらくして
脳の満腹中枢が刺激されるため、満腹感を覚えるのにはある程度時間がかかります。
食べるペースが速いと、満腹を感じる前に食事が終わってしまい、欲求不満が残ります。
また、会話を楽しみながらゆっくり食べると、食事制限のストレスも和らいで、さらに効果的です。
糖尿病の運動療法

運動不足は過食とともに糖尿病発症の最大の誘因となっています。
食事療法でエネルギーの過剰摂取を抑え、運動により消費エネルギーを増やせば、糖尿病の改善に大きく役立ちます。
運動療法の効果
- ブドウ糖の消費が増えて、血糖値が低下する。
- インスリンを使うことなしにブドウ糖を消費するので、インスリンの節約になり、膵臓の負担が軽減される。
- インスリン受容体の数が増えたり、働きが活性化することによりインスリンの作用が高まって、血糖値が低下する。
- 筋肉が増えて基礎代謝が高まり、安静時に消費されるエネルギーが増加する。
また、食事療法で起こりやすい筋肉と骨の衰えを予防する。 - 肥満が解消され、中性脂肪やコレステロールを減らすことができ、動脈硬化の予防になる。
- 血液の循環がよくなり、手足のしびれやこむら返りなどの神経障害が改善される。
- ストレス解消になる
以上のように、運動療法は糖尿病の治療にとどまらず、健康的な生活を送るための総合的な効果が期待できます。
しかし、運動をしているからといって、食事療法をおろそかにしては効果は期待できません。
食事療法と並行してこそ効果があることを忘れないようにしましょう。
運動を効果的かつ安全に行うために
運動を効果的かつ安全に行うためには、以下の項目が重要です
- 運動の種類
- 運動強度
- 継続時間
- 実施時間帯
- 運動の頻度
- 運動の種類は、無理なく続けられ、ひとりでいつでもどこでもできるものが適しています。
さらに全身を使った運動が効果的であり、糖分や脂肪の燃焼をよくするために酸素をとりいれながら行う有酸素運動が最適です。
具体的にはウォーキング、ジョギング、水泳、自転車、なわとび、ジャズダンスが相当します。 - 運動が体にかける負担は人それぞれであり、それを知る簡単な方法として運動中の脈拍数を目安にする方法があります。
限界とされる運動強度の40-60%が適当とされており、
となる運動強度が最適です。20および30歳代なら 脈拍数 110-135 40歳代なら 105-130 50歳代なら 100-125 60歳以上なら 100-125
ただし、激しい運動により血圧が急上昇する場合があるので注意が必要です。
特に高血圧、糖尿病腎症、糖尿病性網膜症を合併している方は激しい運動を避けるようにしましょう。 - 1回の運動時間は30分程度が適切です。
運動開始からの15分間は血液中および筋肉内の糖分がエネルギー源となり、15分後から脂肪がエネルギー源として使われます。
このため、肥満の解消を目的とするなら、最低でも15分以上継続して運動することが必要となります。 - 運動を行う時間帯は、血糖値が最も高い食後 1-2時間が最適です。
しかしながら実際には、仕事の関係などで都合よく時間がとれるとは限らないため、無理なく組み込める時間に行うようにすればいいでしょう。
ただし、インスリンや経口血糖降下薬を使っている方は、早朝や空腹時の運動は低血糖を起こす危険性があります。
空腹時に運動をする前に、パンなどの吸収の遅い炭水化物を食べるようにしましょう。
特に30分以上の運動をする場合は運動中にスポーツドリンクなどの吸収の速い炭水化物を摂るようにして、低血糖を予防しましょう。 - 運動療法により血液中のブドウ糖が筋肉に取り込まれます。
健康な人では、肝臓から糖が放出されるため血糖値はほとんど変化しませんが、糖尿病患者の場合、筋肉へのブドウ糖が急速に取り込まれるため血糖値は低下します。これを運動による急性効果といいます。
この急性効果の持続は2日程度ですので、週に3-4日の運動が勧められます。
糖尿病の薬物療法

食事療法および運動療法を行っても、十分に血糖値の改善を得られないときには薬物療法が必要となります。
しかし、血糖値および合併症の程度によっては治療開始時より薬物療法が行われることは決して少なくありません。
また、薬物療法が一旦導入されても、その後の経過によって薬物療法が不要となることもあります。
薬物療法は経口血糖降下薬とインスリンが用いられます。
経口血糖降下薬にはその作用機序によりいくつかの種類があり、膵臓、腸管、肝臓または筋肉に作用して血糖を低下させます。
糖尿病の病状によって使い分けられますが、2-3種類併用されることもあり、場合によってはインスリンと併用されることもあります。
インスリン療法は不足したインスリンを注射により補い、血糖値を下げる治療法です。
以前は「インスリン療法が導入されると重症」といったマイナスのイメージがありました。
しかし、インスリン療法は速効性があり、確実に血糖値を改善できるため、現在では積極的に導入されています。
特に、膵臓からのインスリン分泌がほとんどない1型糖尿病の方には、発症当初よりインスリン療法が必要です。
また、400を越えるような高血糖状態では、経口血糖降下薬の効きが悪いため、一時的にインスリン療法によりある程度血糖値を低下させてから、経口血糖降下薬に切り替えることも行われます。
インスリンは患者さん自身で注射をするため、入院を必要とすることが多く、仕事の都合等でなかなか導入できないケースが見受けられます。
当院ではより的確な糖尿病治療を目指し、外来にてインスリン療法を導入して、自己注射の指導を行っています。
低血糖
糖尿病の薬物療法を行うと、血糖が過度に下がりすぎて、低血糖を起こすことがあります。
低血糖には段階に応じて、さまざまな症状があります。
初期段階では、あくび、不快感、空腹感が出現し、さらにだるさ、眼のかすみ、頭痛、吐き気等が出現します。
こうした初期症状を放置すると、震え、動悸、冷や汗といった交感神経症状が出現するようになります。
そして、最終的には意識を失い、けいれんや昏睡に陥ります。
意識を失った場合は、生死に関わることもあるため、一刻も早く治療を受ける必要があります。
低血糖症状を認識し、早い段階でブドウ糖の服用やジュースの摂取をするなどの対処をすることが大切です。
自己血糖測定

日常の血糖値の推移を把握するために、自分で血糖を測定する方法があります。
特に、インスリン療法中の患者さんには、血糖測定機器に保険適応が認められているため、是非活用したいものです。
食前の血糖値のみを測定している患者さんが多いようですが、糖尿病が改善して、HbA1cが8%未満となると、むしろ食後(2時間後)の血糖値の把握が重要になります。
当院では、週に1度、毎食前および毎食後の血糖自己測定を推奨しています。
糖尿病とアルコール

飲酒が糖尿病に直接に悪影響を及ぼすわけではありません。
しかしながら、アルコールはエネルギーが高いにも関わらず、栄養成分がほとんど含まれていません。
さらに酒の肴にはカロリーや塩分の多いものが好まれがちですので、栄養のバランスが崩れやすくなります。
また、酔うと気が大きくなり、ついつい飲みすぎ・食べすぎてしまうことも懸念されます。
飲酒をするなら、栄養バランスに配慮し、飲む前にお酒とつまみの種類・量を決めておくようにしましょう。
糖尿病とたばこ

たばこを吸うと、ニコチンの作用で動脈が収縮し血小板が凝集しやくなり、一酸化炭素の作用も加わっていわゆる「どろどろの血液」になります。
このように、たばこ自体が高血圧、脳梗塞、心筋梗塞の危険因子です。
まして糖尿病の方が喫煙すると、さらに高血圧、脳梗塞、心筋梗塞の危険度が増幅されることになります。これは糖尿病で動脈硬化が起こった状態にたばこで血流をさらに悪くさせた結果です。また、たばこの刺激で舌の味覚が低下すると、濃い味を好むようになり、摂取カロリーが多くなってしまいがちです。
以上より、禁煙が絶対的に必要です。事実、禁煙してから24時間後には心筋梗塞になる危険性が減少することが知られています。たばこを吸っている方は、節煙ではなく禁煙が必要です。たばこを止められずお悩みの方は、ぜひ禁煙外来を受診してください。

糖尿病のまとめ
現在のところ、糖尿病を完治させることはできません。
治療によって血糖値が良好にコントロールされても、糖尿病が治ったといういことではないのです。また、高血圧、高脂血症、高尿酸血症等の他の生活習慣病と比べて、糖尿病は最も治療が困難な病気といえます。糖尿病には失明、透析、足の切断といった負のイメージが付きまとっており、実際にある調査によれば、他の生活習慣病と比べて「糖尿病は怖い病気」と多くの人に認識されています。
血糖値が高いだけでは無症状のことが多く放置されがちですが、合併症を来たさないためにも早期発見、早期治療が重要です。
また、合併症は糖尿病の前段階である境界型から起こりうるため、境界型からの治療を必要とします。
しかし、糖尿病は一生涯の病気であるからといって、決して悲観することはありません。
糖尿病を上手くコントロールしていけば、日常生活を支障なく過ごすことができます。
糖尿病治療の指導や協力は医療スタッフや家族を必要としますが、食事療法や運動療法といった基本的な治療は、患者さんの日常の生活の中で実践されてゆくのです。
事実、患者さんの自己管理が最も治療効果に関わっています。
糖尿病という病気に振り回されない生活が送れることを目標に、糖尿病と向き合って治療に努めましょう。